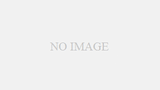KATOからEF55型電気機関車、2023年8月に発売予定 旧型客車セットも
KATOから、2023年8月にEF55型電気機関車の製品化が案内されています。
モデルとなるのは、静態保存から動態保存へと復元された国鉄末期の1986年(昭和61年)頃で、これ以降は高崎第一機関区(現在の高崎車両センター)に所属していました。
また、牽引される客車として、同時期に高崎客車区(同じく現在の高崎車両センター)に所属していた旧型客車も7両セットで製品化されます。
こちらはスハ43系を中心に救援車のスエ78を含む編成で、EF55同様に国鉄末期の1986年ごろの姿をプロトタイプとしています。
スエ78とはあまり聞かない車両ですが、終戦直後の車両不足の折、戦災で使用不能になっていた車両の部品を利用して間に合わせで製造された、70系客車と呼ばれるグループの車両です。
その中でもこの当時在籍したスエ78-15は、もともとはスハ32系のスロシ38-16(登場時はスロシ38010)として1935年(昭和10年)に製造された車両で、1944年(昭和19年)にマハシ49-21へと改造、その後戦災を受けオハ77-8として復旧され、さらにオハ78-8、マユニ78-21を経て最終的にスエ78へと改造されました。
スエ78形は救援車と呼ばれる車種で、災害や事故の際に資材・人員を現場に運搬する役割を担った車両です。特にスエ78形は種車であるスロシ38形譲りの3軸台車を履いていることが特徴でした。
なお、KATOとしてもかなり力が入っている模様で、特設サイトも立ち上がっています。
早々と受付終了も 在庫のあるお店は少な目
発売予告からあまり日が経過していませんが、ファンの間でも人気が高い模様で、2023年4月現在23日現在、早々と売り切れとなっているサイトも多いようです。ご予約は早めのほうがいいかもしれません。
KATO 3095 EF55 高崎機関区
KATO 10-1805 旧型客車 高崎運転所 7両セット
EF55型電気機関車とは? 製造当時は世界的な流線型ブーム
EF55型電気機関車とは、1936年(昭和11年)に国鉄の前身にあたる鉄道省が製造した電気機関車で、合計3両が製造されました。
1930年代になると、ヨーロッパでは航空機や自動車が台頭し、鉄道の利用客は減少に転じることとなりました。この対抗策として鉄道車両の高速化が進められ、ドイツでは1931年に実験車両ながら200㎞/hを超える速度を実現、この成功を受け新たに開発された車両を使用して1933年にベルリンーライプツィヒの286㎞を最高速度160㎞/h、所要時間にして2時間強で結ぶ列車が登場しました。
こうした高速運転を行う特性上、車両のデザインもできるだけ空気抵抗を減らす必要があり、必然的に流線型が採用されることとなりました。
この結果、特に高速運転を行わない車両でも、流線形デザインを取り入れることが流行し、1930年代の鉄道界は世界的に流線形の車両が数多く製造されました。
日本においても、1929年(昭和4年)にはC51形蒸気機関車61号機の前面や運転席周りを半流線形に改造。何が目的だったのか何とも言えないスタイルでしたが、この結果をもとにC53形の43号機を本格的に流線型のボディへと改造し好評を得たことから、続くC55形も半流線型として製造されました。

実のところ、当時の日本の営業速度では、流線型にしたところでそれほど空気抵抗の軽減になるわけでもなく、製造や整備の手間が増えるだけでしたが、世界的な流行を受けて鉄道省だけでなく私鉄でも流線形車両を導入する例が相次ぎました。

EF55は、こうした背景の中で流線型を持った直流型電気機関車として、当時主力であったEF53をベースに製造されました。
車体は流行の流線型を採用し、さらに全体的な車両美を高めるためリベット打ちから電気溶接が全面的に採用、流線型を強調するため前面の連結器は格納式となっていました。
とはいっても、流線型となったのは片側のみで、もう一方は切妻型の何の変哲もないスタイルとなり、構内での入換運転程度の設備しかありませんでした。流線型側には先輪が2軸なのに対し、非流線型側は1軸となり、足回りも左右で非対称という構造でした。
こうしたスタイルのおかげで、当初投入された東海道本線では、蒸気機関車同様折り返し時には転車台で向きを変える必要があり、この手間を嫌ったおかげで3両という少数の製造となったようです。
ただし、製造後まもなく非流線型側の運転台も整備され、どちら向けでも走行できるように改造されています。
戦前から戦中には東海道本線で優等列車の先頭にも立ち、この1号機は1945年(昭和20年)8月3日、沼津機関区で停車中に機銃掃射を受けるという被害を受けています。運転室内には、この時できた破損個所が今なお残っています。戦後まもなくして高崎線や上越線へと転属、台車カバーなどの一部が撤去された状態で普通列車や貨物列車の牽引にも使用されました。
しかし、依然として方向転換の手間や整備性の悪さは改善されず、後継の機関車が増備されるにつれ運用は縮小、1964年(昭和39年)までに3両とも廃車となりましたが、1号機は国鉄の教育施設で使用されることとなり、解体は免れました。
その後1号機は高崎第二機関区で留置されていましたが、1978年(昭和53年)には将来鉄道記念物となり得る、歴史的文化価値の高いものとして準鉄道記念物に指定され、撤去されていたカバーもこの時に復元されています。
さらに1986年には、本線走行が可能な状態に復元され、6月24日付で車籍が復活。JR東日本に引き継がれ、その後はイベント列車として上越線などを中心に使用されることとなりました。その外観から、キャラクター「ムーミン」の愛称がつけられたのもこの頃でした。
しかし、機関車自体の老朽化と補充部品の枯渇などにより、2009年に引退。しばらくは車籍のある状態でしたが、2015年に埼玉県の鉄道博物館へ所蔵されることとなりました。